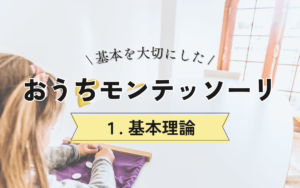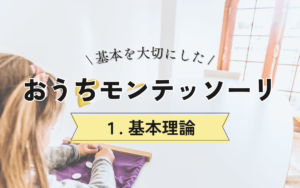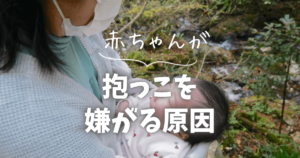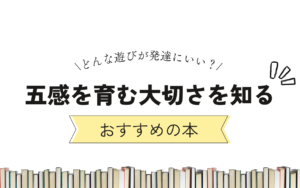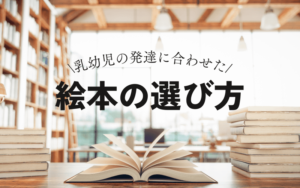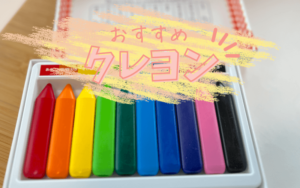本記事のリンクには広告が含まれています。
モンテッソーリ教育とは何?おうちモンテッソーリとの違いって?
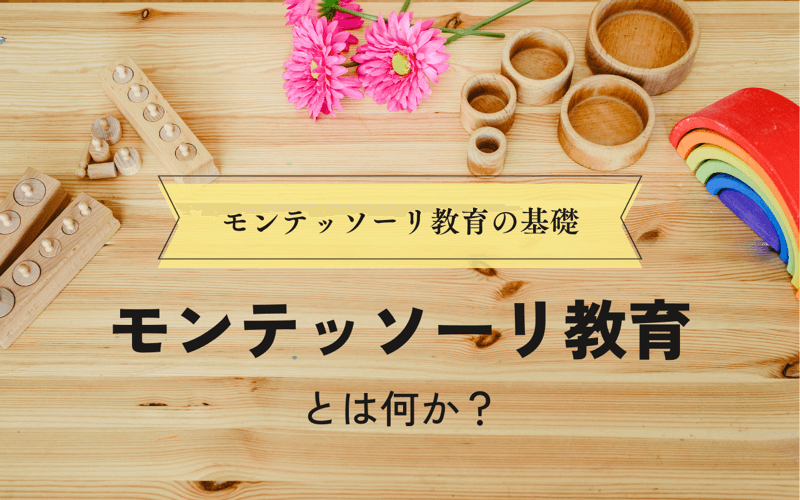
こんにちは!保護者向けに知育講師をしている まなです。
今回は、おうちモンテッソーリを始める前に知っておきたい基本のお話です。
- モンテッソーリ教育とは、どこのどんな人が考案したどんな教育法なのか?
- おうちモンテッソーリとモンテッソーリ教育の違いとは?
- 教師によってモンテッソーリ教育の内容が違うのはなぜ?などなど
おうちモンテッソーリの場合、実は、教師×生徒の数だけやり方が存在します!
勉強熱心な方は、色んなモンテッソーリ本を読まれて知識を深めてらっしゃるかと思いますが、勉強すればするほど、どのやり方を参考にしたら良いか分からなくなりませんか?
人によって、言ってることが微妙に違ったり、活動内容が違ったり・・・。
私も勉強しているうちに迷子になりそうだったので、ちゃんとマリア・モンテッソーリ自身の著書に基づいて学習をしてみました。
 まな
まな今回は、モンテッソーリ教育に足を踏み入れる前に知っておきたいことを少しまとめてみてます。
モンテッソーリ教育の創設者とは?
モンテッソーリ教育の創設者はマリア・モンテッソーリ(Maria Montessori)(1870-1952)イタリアの医師です。
精神科病院での研究の一環として、精神障害を持つ幼児たちのための教室を設立。
そこで幼児たちの行動や学習の観察を通じて、彼らが環境の中で自主的に活動し、興味に基づいた学びを通じて自己成長することに気づきました。



教師の指導なしでも自分自身で学ぶという自己教育の能力(自己教育力)を持つことを発見したのです。
そこからモンテッソーリは独自の教育理論と方法を形成し、モンテッソーリ教育の基礎を築いていきました。
モンテッソーリは、子供たちが自己教育力を発揮できる環境を整えることの重要性を説いています。


彼女の教育方法は、子供たちの個別の能力や発達段階に合わせた環境の提供を特徴としています。



モンテッソーリとは人の名前です。なので、私は敢えてモンテと省略しないようにしてます。
モンテッソーリ教育とは何?どんな内容を学ぶの?


モンテッソーリ教育では大きく5つの分野に分け、教育を行います。
- 日常生活の練習
- 感覚教育
- 算数教育
- 言語教育
- 文化教育
この5つの分野は相互に関係し合っており、分野こそ違えど切り離されないものです。
日常生活の練習部分については、国によって文化や生活様式が異なります。
それぞれの国に合った方法を取り入れたり、変えたりして応用する必要がある部分です。
モンテッソーリ教育では母国語学習を優先します。
なお、学ぶ順番には重要な意味がありますので、この順番でなければ効果が薄れます。
また、それぞれの分野や活動に敏感期と呼ばれる、子どもが最も知識を吸収しやすくなる学習に適した時期があり、これは個人によって異なるものです。
子どもたちを観察する中から大人がその時期を見極め、適切な時期に適切な環境を用意したり、強制することなく活動に導いていくという流れで教育を進めます。
『敏感期』
この言葉はモンテッソーリ教育でも頻出の有名な単語なので、ぜひ覚えておきましょう。
- 5つの分野があり学ぶ順番がある
- 個人によって学びの時期が異なる(年齢ではない)
この2つのポイントを知るだけでも、家庭でモンテッソーリ教育をされる方には大きな違いが出てくると思います。
現在、日本で流行ってるおうちモンテッソーリのほとんどは、日常生活の練習だけで終わっていたり、5つの分野の垣根がなくなった形で年齢基準にプランが進められていたり・・・



本来の精巧なシステムが失われた状態で蔓延している印象です。
おうちモンテッソーリとモンテッソーリ教育の違いとは?


おうちモンテッソーリは本来のモンテッソーリ教育とは異なり、各家庭でアレンジが違うものです。
モンテッソーリ園では教具も一式揃えて環境が整った生活を行うため、本来のモンテッソーリ教育を受けられます。
ですが、おうちモンテッソーリは、ゴール設定に自由度が出る分、目指す目標によってモンテッソーリ教育を取り入れる濃度が異なります。


例えば、子どもの日常生活における自立を促すことに焦点を当てた目標であれば、そこに向けた活動を行います。
知性を伸ばすことに焦点を当てた目標であれば、日常生活の自立に加え、より学習的要素を加えたモンテッソーリ教育の活動を取り入れることになります。
おうちモンテッソーリ では、“教具を使わずに”“日常生活を自立させる”という方法がメジャーになっているため、どうしても、本来のモンテッソーリ教育とは異なるものになってしまいがちです。
子ども主体であれば、教具や形式張ったカリキュラムに堅苦しく縛られなくても良いという考えもありますし、そうじゃない、という意見もあります。
考え方は人の数だけあるので、それぞれの価値観で違うのだと思います。



私はどちらかというと教具あり推奨派です。
モンテッソーリ教育の分野は多岐に渡り、また、互いに作用し合う繋がりを持ったものです。
教具を使わない選択になると、本来の繋がりが絶たれ、相互作用が弱まります。
それでも、原理を知って向かえば教具なしでも出来なくはないかもしれません。
モンテッソーリ教育の全体構造を知った上で『おうちモンテッソーリ』としてカスタマイズする方が効率的になりますが、世に出回っているモンテッソーリ本は全体構造よりも実践方法にスポットライトを当てたものが多いような気がします。
方法の例示があればすぐにでも真似して今日からでも簡単にモンテッソーリ教育を始められちゃいますからお手軽ですよね。



ですが、出来れば全体構造(基本)を知ってからが絶対におすすめです!
全体構造を頭に入れている人たちは、力を入れる場所と抜く場所を理解出来ているため、おうちモンテッソーリにおいても本来の効果が得られやすくなります。
本に書いてあることを同じように実践しようとしても、本の著者のように解釈の土台となる部分が無ければ、方法を真似ているだけなのでどこかで差異が生まれ、つまずいて、中には、迷子になってしまう人も出て来るということです。
教育原理が分からないまま実践するため、起こり得る問題だと思います。
堅苦しい形式ばったカリキュラムを捨てたはずが、結局は、本で言われる手順の形式に縛られているという矛盾に気づかなければなりません。
モンテッソーリ教育の仕組みを知ると、おうちモンテッソーリをしていても、どこにつまずいたのか分かるようになります。
我が家らしいおうちモンテッソーリを手に入れるためには、やはり、基本知識の習得が大切ではないでしょうか。
その知識習得をするためにどうすれば良いのか?
なるべく、マリア・モンテッソーリ自身が書いたものや言葉に基づく本に目を通すようにしてください。



そうすれば、本当の意味でおうちモンテッソーリを自由に出来るようになるのだと思います。
さいごに
「モンテッソーリ教育とは何?」を少しかいつまんでまとめてみましたがいかがでしたでしょうか?
私がこの記事を書こうと思ったのも、世の中に溢れているモンテッソーリ教育の矛盾について、問題提起したかったからです。
モンテッソーリ教育は勉強すれば勉強してみるほど、驚くくらい緻密に練られた教育法であることを知りました。
そうして世の中に目を向け直してみると、モンテッソーリと謳われてるもののほとんどが、マリア・モンテッソーリ自身が大切にしていた部分を置き去りにした形で広がってしまっているように見えるのです。
つまり、本来の力を発揮しない形で広まってしまっているということ。
それってなんだか悲しいです。
手作り教具を作るにしても、購入するにしても、基本とする考え方が重要になってくると思います。
そこが分からないまま進めていると、効力を発揮しない危うさがあるのです。
一般的な本でもあまり強調されてなくて読み流してしまうところですが、敢えてその部分に注目しながらおうちモンテッソーリの基本についてお伝えして行きたいと思っています。



ぜひ、基本部分に目を向けてみましょう!