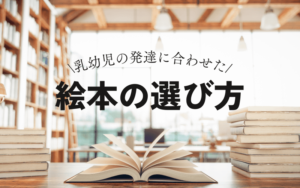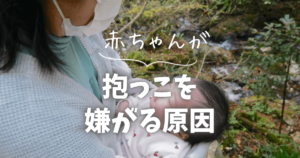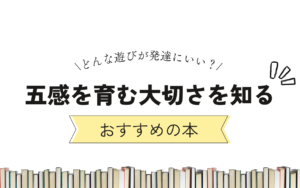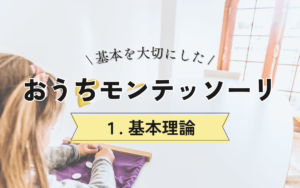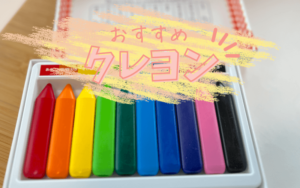本記事のリンクには広告が含まれています。
発達に合わせた読み聞かせ絵本の選び方ガイド
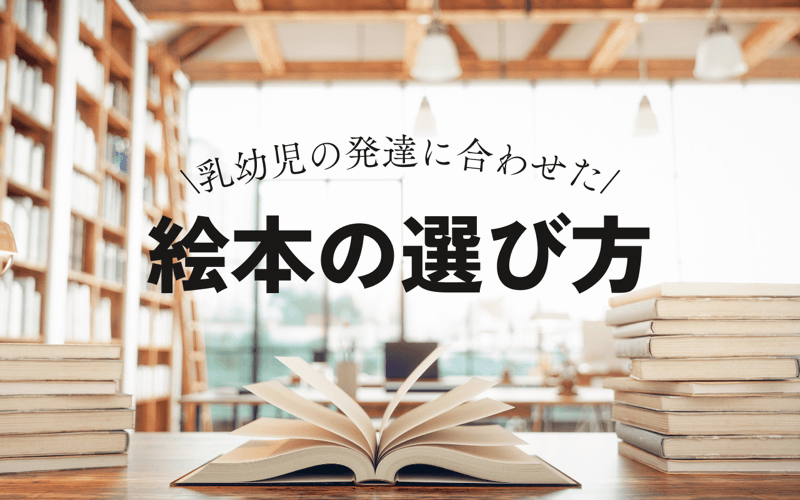
こんにちは!保護者向けに知育講師をしている まなです。
子どもへの読み聞かせって大切だと言われているから、絵本は絶対読んであげよう!そう思われているお母さんたちは多いはず。
でも、実際、どんな絵本を読んであげればいいんだろうか。
 まな
まなその情報ってなかなか入手できなくて困っていませんか。
絵本の選び方って、目的によって変わってくるのですが、今回は、教育的視点で選ぶ方法についてまとめてみました。
読み聞かせのポイントと発達に合わせた絵本の選び方をモンテッソーリ的な考えを取り入れつつお伝えしますね。
読み聞かせのポイント
いつから読み聞かせるべきか?
生まれてすぐでも、生まれる前からでも!
赤ちゃんの聴覚は、胎生5、6ヶ月頃に機能が完成していて音に反応を示すことが研究によって知られています。
また、胎生週数が進むにつれて音への感受性も高まって行くため、聴覚が完成した頃から人の声を聞かせるという意味で読み聞かせても良いと思います。
お腹の中にいる時と生まれてからだと、羊水内で聴いていた音とは異なる聞こえとなるため、実際には同じ声だとすぐに認識するのは難しいです。



それでも、聴覚は音を聞くということで育まれます。
脳を育むための聴覚刺激として読み聞かせの声が優しい刺激を与えてくれます。
読み聞かせの時間の長さとは?
乳幼児期の子どもは集中力が長くもちません。
年齢+1分が目安だと言われています。
1歳児なら2分、2歳児なら3分、3歳児なら4分・・・といった具合です。
最大それくらい。
そこまで満たない場合も普通にあるということ。
夢中になれるものがあった時は目安時間を遥かに超えて集中することはありますが、基本的に子どもの集中時間は短いということを頭に入れておくと良いでしょう。
適切な絵本の冊数は?
最初は少ない冊数から始めます。
大体4、5冊以下で始めると良いです。
慣れたら徐々に冊数を増やしてみてください。
個人によって本への関心度や本を読んで来た冊数など経験値が違うと思うので、その子その子にあった冊数で調整しましょう。
選択肢が多過ぎると、子どもは気が散ってしまいます。



結果、選べなかったり、興味をなくしたり・・・なんてことも。
もしも、選択肢が多いせいで本から気持ちが遠ざかってしまったかなという感じがあれば、数を少なくしてもう一度やり直してみてください。
絵本好きにさせるコツ
子どもは親が夢中になっているものに興味を示す傾向があります。
なので、本に興味を持つ子どもに育てたければ、まずは親が読書する姿を見せると効果がありです。
発達に合わせた絵本の選び方
絵本の読み聞かせ効果に期待したいのは、やはり、言語の発達だと思います。
だからこそ、絵本選びにはつい力が入っちゃいますよね。
選び方に困ったら、次のポイントを参考にしてみてください。
発達に合わせた絵本選び
オノマトペ(擬声語・擬音語・擬態語)は感覚的な部分になるので、ぜひ小さい頃から読み聞かせて、身につけさせていってください。
日本人は特にオノマトペを使う人種であり、日本人としてのアイデンティティに繋がります。
音も面白いので、赤ちゃんにとっても言葉の楽しさに興味を持つきっかけにも。
最初は身の回りのものの名称を覚えるところから始めるため、絵本の内容も名詞が主体になってるものを選びます。
学習する母国語によって覚えやすい品詞の順序が異なるというデータがあります。
日本語が母語話者である日本人の場合、最初は名詞の方が覚えやすい傾向にあるため、子どもが吸収しやすい言語に触れさせる機会を増やすと良いでしょう。
子どもの話し方に文法が出現しだすと、名詞優位だった吸収性が動詞を覚えやすくなる傾向に切り替わります。
つまり、単語だけじゃなく言葉として話し始める頃には動詞により多く触れさせてあげると良いですね。
名詞がある程度増えたら、早め早めに、新しい単語が混ざっている本を取り入れていくと言葉が育つ手助けになります。
絵本は言葉を増やす手助けになるのと同時に、色んな感性を育てるキッカケにもなります。
文学作品や想像力をかきたてる作品を徐々に読んでいくと情緒も育みます。



他にも以下のポイントを大切にしてみてください。
- 日本語が正しいもの
- 接続詞や助詞がしっかりしているもの
- 間接的な体験知識を増やせるもの
- 読み聞かせの無理強いはしない
参考までに、絵本を使った場面=名詞優位、おもちゃを使った場面=動詞優位になる傾向です。
絵本の読み聞かせだけにこだわらず、おもちゃを利用しても良いですよ。
普段使わないような単語を引き出すきっかけになります。
「何歳からこんな本にしましょう」というよりかはお子さんがどれくらいの言葉を吸収しているか意識しながら内容を選ぶと良いかもしれません。
名詞の理解が深まって来たら動詞、形容詞や形容動詞…と徐々に言葉の種類を増やしたテーマのものを取り入れていく、そんな感じの流れでいいと思います。
自分の興味関心を表現できるようになっているのであれば、その興味を広げてあげられる図鑑なども取り入れていくと良いですね。



自分で本を見て選ぶのは苦手だという方は、「こどものとも」や「くもんの推薦図書一覧」の本を選ぶと良いですよ。(モンテッソーリ的ではないですが)
絵本は間接的な体験知識を増やすのにもってこいのツール。
直接的に経験するには難しい内容でも、本を通してなら間接的に経験を、たくさん増やすことが出来ます。
そうして知識として身につけ、いつか実際に経験した時に「あ、コレ、本のやつだ!」という感動に結びつくんです。
子どもってなかなか読み聞かせても聞いてくれないですよね。
この絵本あんまり好きじゃないのかな?って思うこと、多々ありますが、ある時、突然どハマりする日が来るようです。
地道に読み聞かせ・・・ですね。
ただ無理強いは禁物。
絵本は楽しむものです。
押し付け的な読み聞かせは控えましょう。
嫌がっているのであれば、その意思を尊重してあげてください。
無理やりに進めてしまうと本嫌いになる原因となります。
0歳から2歳の絵本選び
小さい子どもはまだ現実と空想の世界の区別がつきません。
モンテッソーリ式の絵本選びでは、脳がまだ未熟な年齢においては、なるべく現実に即している内容の絵本を選びます。
- 動物が喋っている
- 物や動物の比が現実と違う(虫と動物が同じ大きさなど)
こういうのは避けます。
多分、モンテッソーリを勉強されてる方は「なるべく写真がいい」というのを聞かれたことがあるかと思います。
縮尺もおかしくはならないし、現実に即した形で写るから、なるべく写真なのです。
現実的であれば絵でも構わないと思います。
今回は読み聞かせ絵本というテーマなので絵本での方法をお伝えしておりますが、実物で教えられるなら実物で名称を教えてあげてください。
生まれて来た子どもたちは、生活をしていく上で身の回りのものに関心を持ちます。
生活に関係のあるものを絵本で見せていくと良いですよ。
食べ物、動物、形、色が意識されたものもいいですね。
絵本に限らず、身の回りにあるもので名称を教えていくのも大切です。
- 絵本の絵と文章が一致したものを選ぶ
- 正しい日本語で書かれているものを選ぶ
- 赤ちゃん言葉や幼児語がないものを選ぶ
文字のない絵本タイプでは絵を見せて、その時々で読み聞かせる言葉が変わるので、表現力を豊かに育みます。
ただ、読み聞かせる保護者の語彙力にかかってくるので、そういうのが苦手な人は文字があるものを最初から選んだ方がいいかも?
負担にならないやり方を選んでくださいね。
3歳からの絵本選び
生活絵本などで人の動きを学びます。
動作や動きについて説明がある絵本を選べると良いです。
動詞の語彙を増やせるように。
人との関わりについてなど徐々に取り入れていけると良いですね。
4歳からの絵本選び
個人差がありますが、4・5歳くらいからだんだんと現実と空想の世界がはっきり区別できるようになります。(6歳くらいは特に)
動物は喋らないっていうのが分かり、過去・現在・未来の時間的概念もしっかりして来ますね。
物語絵本、文学作品、科学絵本など想像力を使う絵本がおすすめです。
さいごに
年齢や参考図書はあくまでも目安です。
子どもの成長や興味は個人によって大きく異なります。
読み聞かせ絵本については、色んな流派や考え方が存在するので、これが正しいって言えるものがありません。



今回伝えたのも一例だと考えてください。
ご家庭ごとで、重きを置いてる部分も違うと思います。
なので、絵本選びについては、ご家庭で大事にされている部分(価値観)を優先する形で選べば、納得のいく読み聞かせができるのではないでしょうか。
必要だと思う部分を取捨選択し、参考にいただければと思います。
私も自分で出来る範囲のことをしています。
無理して教育法にがんじがらめになるよりも大切なのは継続できる環境です。
我が子の発達段階に合ったものを読み聞かせ続けていけると良いですよね。



ただ、どの流派・やり方にしても、絵本を好きになってくれることが大事という部分は共通だと思います。