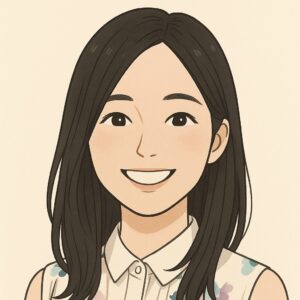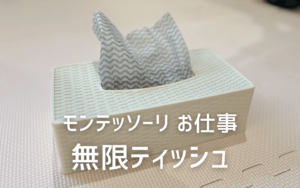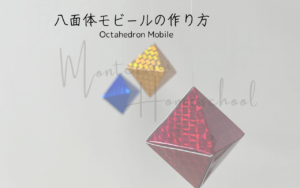モンテッソーリ教育に興味を持ち、おうちモンテッソーリを実践しようとすると、多くの方がまず「教具」や「おもちゃ」に注目します。
SNSやブログで紹介される手作り教具に憧れ、「これを準備しなければ!」と意気込む方も少なくありません。
しかし、その過程で見落とされがちな本質があります。
モンテッソーリ教育の目的は、教具を揃えることではなく、子どもの自発的な成長を助けることです。
そのためには、手作り教具よりも、子どもが自分でできる環境を整えることが重要になります。
本記事では、おうちモンテッソーリを実践する際に生じやすい誤解を解きながら、モンテッソーリ教育の本質に迫ります。

・幼児教室指導員
・おもちゃコンサルタント
・知育玩具アドバイザー
・国際モンテッソーリ資格 etc.
3歳子育て中の 1児母。モンテッソーリ教育に対して最初は懐疑的だったが理論を学ぶうちに解釈が変わる。一般的な幼児教室のカリキュラムを学んだほか、現在、国際モンテッソーリ教師養成コースにて最も正統なモンテッソーリ教育法を修得中。
手作り教具やおもちゃが先行して我が子の興味が置き去りに
モンテッソーリ教育を始めると、多くの親御さんが「どんな教具を用意すればいいの?」と考えます。
確かに、教具は子どもの発達を助ける重要な要素ですが、それが目的になってしまうと、本来の子どもの興味や発達の流れを無視することになりかねません。
例えば、手作りの「色水遊びセット」や「ビーズ通し」を用意しても、子どもが興味を示さなかったり、すぐに飽きてしまうことがあります。
そのとき「せっかく作ったのに…」と残念に思うかもしれません。
しかし、それは子どもが発達段階に合っていない、または他のことに興味を持っているサインかもしれません。
大切なのは、「教具を使わせること」ではなく、子ども自身の興味を尊重し、それに合わせた環境を整えることです。
 まな
まな子どもの観察を通して、興味を持っているものに対して手作り教具やおもちゃを考えるのであって、教具やおもちゃに子供を合わせるのではありません。
敏感期の一覧表に閉じ込められた子どもたちの活動
モンテッソーリ教育では、子どもが特定の能力を集中的に発達させる「敏感期」があるとされています。


例えば、1歳半から2歳ごろは「運動の敏感期」、2歳から4歳ごろは「秩序の敏感期」など、発達の流れに応じた敏感期が存在します。
しかし、この敏感期のリストを参考にしすぎるあまり、「この時期だから、この活動をさせなきゃ!」と考えてしまうことがあります。
例えば、「3歳だからひらがなの敏感期だ」と思い、文字カードやおもちゃを用意したのに、子どもはそれに興味を示さず、むしろお箸の練習ばかりしたがる…といったこともあります。
こうした場合、親は「まだ早すぎたのかな?」と不安になったり、「もっと興味を持たせるにはどうしたらいいんだろう?」と考えてしまうかもしれません。



私も、理論について深く学んでいない頃、これで失敗しました。
しかし、モンテッソーリ教育の本質は、「敏感期の一覧表に当てはめること」ではなく、子ども自身を観察し、その興味を大切にすることです。
敏感期の一覧表があると、どうしてもその表に当てはめて考えようとしてしまいます。
ですが、表にある敏感期はあくまでも一部例に過ぎないことを知っておきたいです。
一般的に大きな括りで紹介されている敏感期とは別に子どもそれぞれで無数の敏感期があります。
子供達の興味を見つけるヒントとして、娘の敏感期の記録が役に立つかもしれないので、ぜひ見てみてください。
娘の敏感期
子どもたちには思った以上にたくさんの敏感期が存在します。



こんな行動を見かけたら、敏感期かも。
我が子の観察から興味関心を見つけることが本質
子どもは自分の発達に必要なことを、本能的に求めています。
そのため、親がすべきことは「何をさせるかを決めること」ではなく、「何に興味を持っているのかを観察すること」です。
例えば、こんな姿を見たことはありませんか?
- おままごとよりも、本物の野菜を触ったり、お皿を洗いたがる
- おもちゃのハンマー遊びよりも、本物の工具に興味を示す
- ひらがなよりも、看板の文字やカレンダーの数字を気にする
- おもちゃの携帯より本物の携帯を触りたがる
子どもは本物を欲しがる、とよく言いますよね。
子どもが求めているのは、単なる遊びではなく、生活をするためのスキルアップ…本物を好むのは実生活に役立つスキルを欲している証拠です。



こうした興味は、子どもが「今、これを学びたい」と思っているサインです。
この興味を大切にし、必要な環境を整えることがモンテッソーリ教育の本質なのです。
我が家も週1で子どもの家に通っていますが、そこで何かを育ててもらおうという気はなく、自宅とは違って、たくさんの活動ができる新鮮な環境で、新しい興味を見つける機会の場所として娘に行ってもらってる感じです。
モンテッソーリ園に丸投げできればそれが一番楽ですが、我が家のように、物理的に通えない家庭もたくさんあると思います。
そういった家庭では、物を与えるモンテッソーリ教育ではなく、「大人が物との架け橋になる、そんなモンテッソーリを目指していきましょう!」と呼びかけたいです。



我が家では、基本的に、極力、生活の中にある物を使っておこない、どうしても、子どもの能力に合わない難易度になってしまってる部分だけ、手作り教具やおもちゃなどで補う感じです。
「日常生活を子どもサイズに」の解釈
モンテッソーリ教育では、子どもが自分でできる環境を作ることが大切だとされています。
これは、「手作り教具を揃える」ことではなく、日常生活の中で自立できる環境を作ることを意味します。
例えば、以下のような環境を整えるだけで、子どもは「自分でやりたい!」という気持ちを満たせるようになります。
手を洗う環境
- 洗面台に踏み台を置く
- 子ども用の小さなタオルを用意する
自分で服を選ぶ環境
- 子どもの手が届く場所に服を置く
お片付けしやすい環境
- おもちゃの収納をシンプルにする
- ものの定位置を決める
食事の環境
- 子どもサイズのカトラリーを用意する
- 小さなピッチャーで水を注げるようにする



このように、手作り教具を作って並べることが目的なのではなく、「子どもが自分でできる環境を整えること」が、最も大切なことなのです。
大人の感覚での楽しそうを付加する必要はない
子どもが興味を持てるようにと、大人は「楽しく遊べる工夫」をしようとすることがあります。
例えば、教材にイラストをつけたり、キャラクターを描いたり、装飾をしたり。
モンテッソーリ教育においては、「楽しいからやる」ではなく、「興味があるからやる」という考え方が大切です。
大人にとっては退屈に見える単純な活動も、子どもにとっては「できるようになりたい!」という強い意欲を伴うことがあります。
例えば、スポンジで机を拭く、ひたすらボタンを留める、豆を移し替えるといった作業は、大人から見ると単調でも、作業そのものが、子どもにとっては夢中になれる活動なのです。
モンテッソーリ教育では、「子どもが自発的に取り組める環境を整えること」が大切であり、大人が「楽しい工夫」を付け足す必要はありません。
むしろ、大人が余計な演出をしすぎると、子ども本来の興味や集中を妨げることになってしまうこともあります。
子どもが何かに熱中しているとき、それがシンプルな作業であっても、そのまま見守ることが大切です。
大人の感覚で「もっと楽しくしよう」と介入するのではなく、子どもが自分で楽しさを見出せる環境を整えることを意識してみましょう。
道具全てを買い揃える必要はない
モンテッソーリ教育において、教具や道具を買い揃えることが目的ではありません。
必要なのは、子どもが興味を持ち、自分でできる環境を整えることです。
例えば、モンテッソーリの「水の移し替え」の活動は、専用の教具を買わなくても、家にあるピッチャーとコップで代用できます。
「ボタンかけの練習」は、専用の教具ではなく、実際の服で練習すればOKです。(我が家の場合、教具ではなく、服での練習を好みました)
モンテッソーリ教育の本質は、「特別なものを揃えること」ではなく、「日常の中で子どもが自分でできる機会を増やすこと」です。
日常生活の練習が全ての活動の基盤となるため、最優先とされる活動となりますが、これは家庭で取り入れるモンテッソーリではモンテッソーリ園よりも充実した学びを提供することも可能です。
もちろん、数教育や言語教育に進んでいく中で、 モンテッソーリ教具は効率的な学びを提供してくれるため、他の学習教材を買うより断然教具を買う方がおすすめですが、原理を知っていれば、他の方法で学びのサポートをすることはできます。
モンテッソーリ教育の基礎知識
まとめ
モンテッソーリ教育を実践しようとすると、つい「教具やおもちゃを準備しなきゃ」と思いがちですが、本当に大切な目的は「子どもが自分でできる環境を整えること」です。
色んな物を買い揃えることが必要な大変な教育法のようになってしまっていますが、実際に重要なのは子どもたちの興味です。
- 手作り教具やおもちゃよりも、子どもの興味を優先する
- 敏感期の一覧表にとらわれず、子どもの観察を大切にする
- 日常生活を子どもサイズにすることで、自立を助ける
- 大人の感覚での楽しいを付加しなくても子どもたちは作業そのものを楽しめる
- 特別な道具を揃えなくても、家にあるもので実践できる



おうちモンテッソーリを始める際は、「何を買うか」ではなく、「どう環境を整えるか」を意識してみましょう。