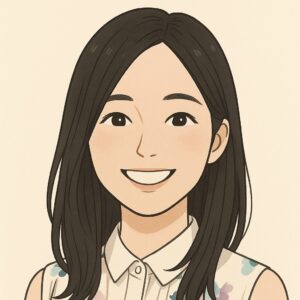歩く敏感期って全員に訪れるものですが、意外にスルーされがちです。
でも、真剣に、この敏感期と向き合ってあげると、将来的に運動知育に頭を悩ませなくてよくなるというメリットがあります。
我が家では1歳1ヶ月ごろから、敏感期に入ったと推測。
 まな
まな歩くことが知育になるなんて誰も思いませんよね。でも、実は、歩くだけでこんなにも身につくものがあるって言うのを今回はたくさんお伝えしたいと思います!


・幼児教室指導員
・おもちゃコンサルタント
・知育玩具アドバイザー
・国際モンテッソーリ資格 etc.
3歳子育て中の 1児母。モンテッソーリ教育に対して最初は懐疑的だったが理論を学ぶうちに解釈が変わる。一般的な幼児教室のカリキュラムを学んだほか、現在、国際モンテッソーリ教師養成コースにて最も正統なモンテッソーリ教育法を修得中。
歩く敏感期の様子ってどんな感じ?


我が家は生後10ヶ月の終わり頃から歩き始めていました。
0歳から歩いていたわけですが、とにかく歩く敏感期はすごかったです。
自分でどこまでも歩きたがります。
特に目的地はなく、散歩も立ち止まっては歩く、道草、を繰り返して動き回るのですが…
1日の平均歩数?みたいなのをApple Watchからお知らせしてくれたのですが、歩く敏感期では、毎月、歩く距離が伸びていきました。
気がつけば1日8km以上歩いていた…なんて月もありました。
| 年齢・月齢 | 1日平均距離 | 月間最高 |
|---|---|---|
| 1歳0ヶ月 | 2.2km | 3.3km |
| 1歳1ヶ月 | 2.8km | 5.3km |
| 1歳2ヶ月 | 4.6km | 6.3km |
| 1歳3ヶ月 | 4.0km | 5.5km |
| 1歳4ヶ月 | 4.7km | 7.5km |
| 1歳5ヶ月 | 4.5km | 6.9km |
| 1歳6ヶ月 | 4.9km | 8.1km |
| 1歳7ヶ月 | 4.7km | 8.8km |
| 1歳8ヶ月 | 4.9km | 7.8km |
| 1歳9ヶ月 | 5.0km | 8.0km |
| 1歳10ヶ月 | 4.8km | 7.4km |
| 1歳11ヶ月 | 4.3km | 7.6km |
| 2歳0ヶ月 | 4.3km | 8.0km |
| 2歳1ヶ月 | 4.2km | 7.7km |
| 2歳2ヶ月 | 3.9km | 6.0km |
| 2歳3ヶ月 | 3.7km | 5.7km |
| 2歳4ヶ月 | 3.3km | 4.4km |


私は娘より動いていない方なので、娘はもっと移動していることになります…。
歩く場所は足元が悪い場所、坂道、階段、どんな場所でもとにかく歩きます。
止められても歩きます。大人の方がもう帰ろうよと誘っても歩くことをやめません。
娘が生まれる前のこのウォーキング計測は0.5km未満の生活をしており、月間最高なんて1kmが月1回あるかどうかみたいなレベルで生活してました(笑)
明らかに娘が歩いていることにより、距離が増えたと考えられます。



おかげで、妊娠で20kg増量した体重が、産前より痩せるという…
周りから病気かと心配されましたが、単に歩くことに付き合って余分な脂肪が落ちただけです(笑)
歩く敏感期を過ぎると、あれは幻だったのか?というくらい、歩かなくなります。
3歳では散歩に誘っても、お友達が一緒でない場合は、散歩に行きたがりません。
歩く敏感期で育った力・知育効果とは?





とにかく、歩くことで育つのは、体幹です。
娘は1歳になったばかりの頃には安定的に歩いており、坂道もガシガシに、自宅に配置した滑り台も、もはや普通のスロープ感覚で歩いておりてました。
1歳半ごろには激坂を走り下りてました。
かなりの激坂でもこけずに走ることができており、2歳0ヶ月で子どもの家に行った時には、もう体幹が出来上がっているので、4、5歳ですることになる線上歩行が必要もないくらいだと言われたくらいです。
ベビーカーは両手で数えられる程度にしか使いませんでした。(本人が歩きたがって、乗りたがりませんでした)



歩く敏感期では、抱っこも嫌がり、基本的に自分で歩きたがりました。
1歳の足取りとは思えないほど、全くふらつきもなくどっしりとしており、3、4歳のような足取りですたすたと歩いていたので、よく実年齢プラス2歳以上で見られていたほどです。
体幹がすごくて、よくショッピングモールとかに置いてるタイプのオムツ台?に自分一人で登って寝ていることもありました。
ベビーカーや抱っこを嫌がるほど自分の力で歩きたがる強烈な歩く敏感期のおかげで、粗大運動が早いうちから完成していた娘。
体幹を鍛える遊びが世の中にはたくさん紹介されていて、とても努力して手に入れるものという印象がありますが、特別なことをしなくても体幹は身につきます。
もちろん、歩くだけではなく、他の敏感期もあり、そのおかげで並行して鍛えられた感じがあります(また、別投稿で)
運動ができる基礎が歩くことで整いました。
歩くことは粗大運動と言われる全身の運動になりますが、この動きが調整されると、微細運動(手指の活動)も同時に調整されていきます。
ゆえに、実は、微細運動を育てたければ粗大運動をしっかり育てておかなければなりません。



ただ歩くだけだと馬鹿にしてはいけないのだなと。
歩く敏感期に伸ばしたい力・目標とは?
歩く敏感期(1歳半~2歳半頃)は、子どもが歩行能力を発達させ、自立への第一歩を踏み出す大切な時期です。この時期に伸ばしたい力や育てたい力を、目標項目として解説します。
体のバランス感覚と運動機能の向上
- 転ばずに安定して歩く
- 障害物を避けて歩く
- 坂道や段差をスムーズに昇降する
この時期の子どもは、歩くことで体のバランスを取る力を発達させています。
- 段差のある場所を歩かせる(低いステップ、スロープ)
- 平坦な場所だけでなく、芝生や砂地などさまざまな地面を歩かせる
- 平均台や一本橋を歩く遊びを取り入れる
自己制御力(自分の動きをコントロールする力)
- 速く歩く・ゆっくり歩くなどペースを変えられる
- 決められた道を歩ける
歩く速さや方向を調整することで、自己制御力を養います。
空間認識能力の向上
- 障害物をよける
- 狭い場所を通る
- 目的地まで歩く
歩くことを通して、周囲の環境を認識し、自分の体との関係を理解する力が育ちます。
- 家具の間を歩かせる(ソファの隙間、テーブルの下など)
- トンネルくぐりやフラフープをくぐる遊びを取り入れる
- 目的地(例:マットの上、ドアの前など)を決めて、そこまで歩かせる
自立心と探索意欲の向上
- 自分の足で歩きたいという意欲を持ち、自分の意思で移動する
歩行が安定すると、子どもは自分の行きたい場所へ行きたくなります。この自発的な動きを大切にしましょう。
- 外で自由に歩ける時間をつくる(安全な公園や芝生の広場など)
- 道端の花や石を観察しながら、探索活動を楽しむ
社会性とルール理解の基礎
- 手をつないで歩く
- 人とすれ違うときにぶつからない
歩くことで、周囲の人との関わり方やルールを学びます。
- 「横断歩道では止まる」「手をつないで歩く」といったルールを伝える
- 公園などで他の子どもと一緒に歩く経験をさせる
- 「道では走らない」「人とすれ違うときはよける」などを繰り返し伝える
歩く敏感期は、ただ歩くことを楽しむだけでなく、バランス感覚や空間認識力、自立心、ルール理解など多くの力を育てる大切な時期です。
おうちモンテッソーリでは、子どもの「歩きたい!」という気持ちを尊重しながら、環境を整えてあげることが重要です。
歩く敏感期に導けた要因って?
どうやって、歩くことに積極的になる子に育てられたか?
振り返ってみたのですが、私的に思い当たるのは抱っこ紐だったと思います。
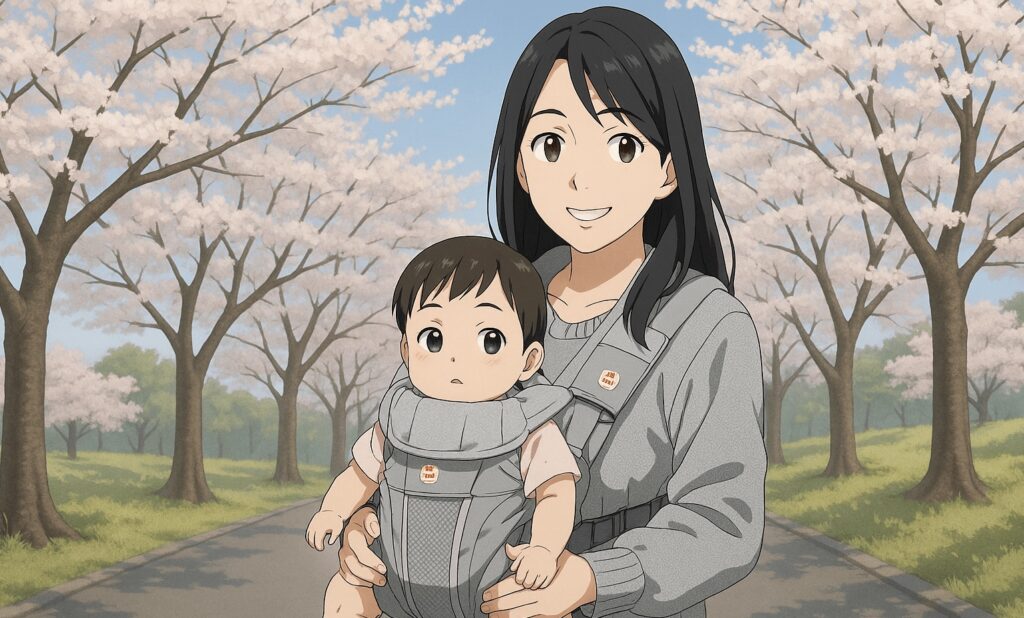
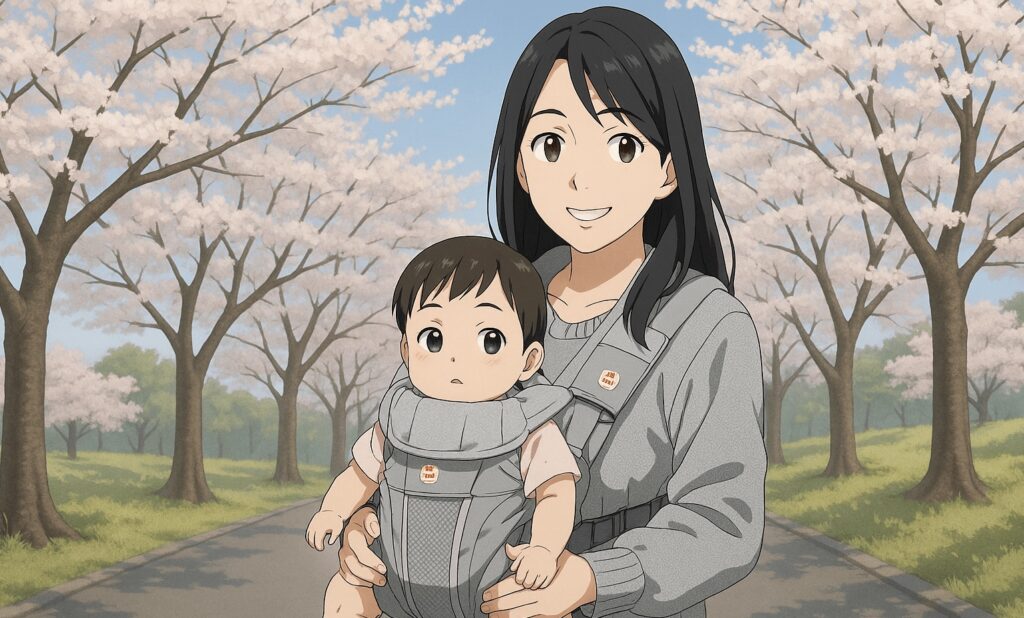
ベビーカーはあまり使わず(レンタルしてましたが)抱っこ紐でお出かけすることが多かったです。
前向き抱っこが出来るようになってからは、常に、私と同じ視界を見るような形でお出かけしていました。
本人も、前向き抱っこの味を知ってからは、お母さん側を向く抱っこは嫌がるようになり、常に前向き抱っこをするような生活でした。
前向き抱っこを出来る期間は、普通のお母さん向き抱っこと異なり、短期間となります。(重心の問題?)
抱っこ紐を使えなくなる期間になったらどうしようかと思っていましたが、その頃には自分で歩きたがる子になっていたので、抱っこ紐すら必要でなくなっていました。
前向き抱っこが、歩く敏感期を強く引き出したのではないかと私は考えています。
早くから、大人と同じ視点で世界を見て歩き、買い物をする時も、お散歩をする時も、常に歩く視点で世界を見ていました。



そのおかげで好奇心が溢れる子になったのかも?
きっと、自分の足で歩けるようになったら、自分で世界を探求したいと、ずっと思っていたのでしょうね…。
子どもは大昔は常に母親の背中に背負われて、一日中、母親のすることを見ながら育つような環境だったという話がモンテッソーリの本の中でもありましたが、現代では、その機会が少なくなっています。
まさに、見て吸収すると言われるこの吸収精神が働く時期に、子どもに世界を見せて歩くということが子どもの学びに繋がるのです。


特別なおもちゃを与えなくても、子どもにとっては、生活そのものが学びです。